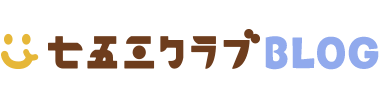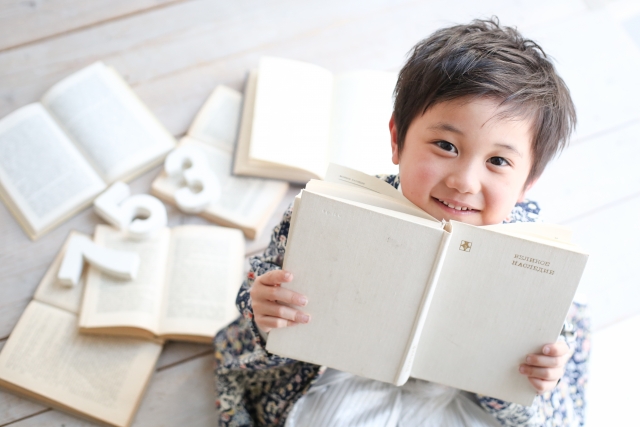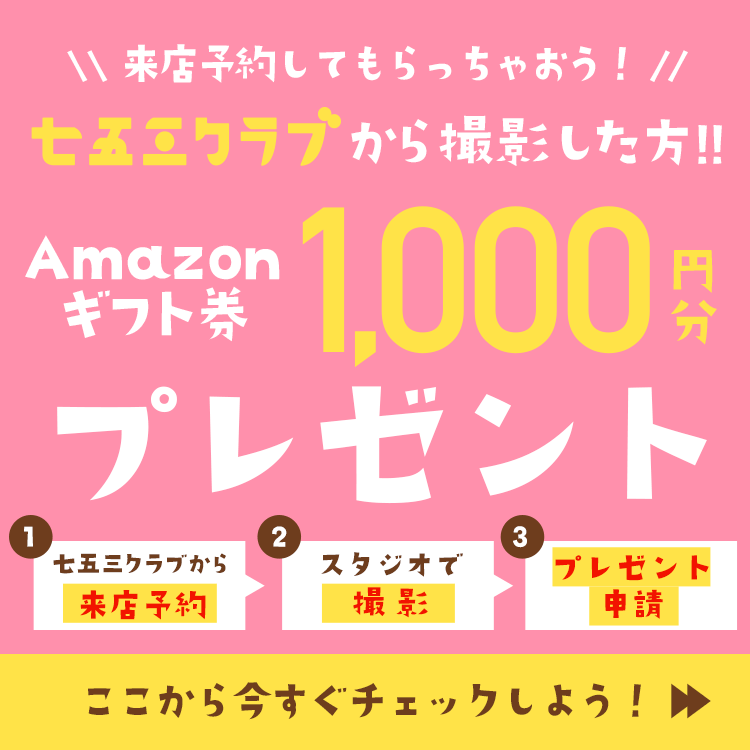七五三は一般的に11月15日に行われますが、近年では11月15日にこだわらず、ほとんどのご家庭がライフスタイルに合わせて参拝日を選んでいます。
そこでこの記事では
「七五三はいつにするべき?」
「そもそも七五三とは?」
「最新の七五三ってどうなってるの?」
といった疑問を解消していきます。
コロナ禍を経て、七五三のカタチも変化しています。
七五三の基礎知識から新しい七五三の定番も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
七五三とはそもそも何?

七五三の意味
日本では古くから子どもは「七歳までは神のうち」だと言われてきました。
昔は幼い子どもの死亡率が非常に高く、7歳まで無事に成長できることは当然ではありませんでした。
子どもが7歳を迎えることで氏神様から氏子として認められ、地域社会を構成する一員として認められてきたのです。
3歳、5歳、7歳の節目となる年齢まで、健やかに成長できたことへ感謝する人生の通過儀礼です。
七五三はいつやるの?

七五三は毎年11月15日にお祝いします。
ただし、必ずしも11月15日にお祝いする必要はありません。
近年では多くのご家庭が都合に合わせて、七五三の日程を選択します。
11月15日として定まった由来
諸説ありますが、江戸時代に徳川五代将軍綱吉が我が子の健康祈願の儀式を11月15日に行ったことが由来だとされています。
旧暦の11月15日は、最良の吉日である「鬼宿日」だったことも一つの通説です。
鬼宿日は鬼が外に出歩かないため、何事をするにも邪魔をされない吉日だとされています。
地域によって七五三の風習が異なる
一般的に11月15日前後に行われる七五三ですが、北海道では寒さが厳しくなる前、10月15日に参拝する風習があります。
お祝いの仕方も地域によって異なり、関西地方は3歳の女の子だけではなく、3歳の男の子もお祝いする地域があります。
また、七五三の文化は関東地方が発祥だったことから、関東地方は全国的に見ても盛大に七五三をお祝いする傾向があるようです。
2023年版七五三スケジュール
2023年は11月15日(水)が平日になるため、七五三の参拝は前後の土日・祝日に集中することが予測されます。
〈11月15日前後の土日〉
- 11月11日(土)赤口
- 11月12日(日)先勝
- 11月18日(土)先負
- 11月19日(日)仏滅
〈11月の祝日〉
11月には例年2回の祝日があり、2023年11月の祝日は以下の通りです。
- 文化の日 11月3日(金)仏滅
- 勤労感謝の日 11月23日(木)友引
〈六曜による日柄の良い土日〉
六曜の日柄を重視する場合は、以下の日程がベストです。
- 11月4日(土)大安
- 11月26日(日)大安
数え年と実年齢の違いは?
七五三のお祝いをする年齢は、数え年と実年齢での数え方があります。
数え年と実年齢のそれぞれの違いについて解説します。
数え年
数え年とは、生まれた日を0歳ではなく1歳とします。
誕生日ではなく1月1日に年を重ねるので、元日になると+1歳です。
実際の年齢から1歳もしくは2歳の誤差が生じます。
実年齢(満年齢)
私たちが日常で使用している年齢の数え方です。
生まれた日を0歳として、誕生日を迎えるごとに+1歳になります。
みんなどっちを選んでいる?
七五三のお祝いは、数え年・実年齢どちらでも問題ありません。
古くは数え年で七五三のお祝いを行っていましたが、現在は実年齢での七五三が一般的です。
ただし、実際には兄弟・姉妹一緒にお祝いをするために、上の子どもは数え年、下の子どもは実年齢といったかたちで両方の数え方を掛け合わせるご家庭もあるでしょう。
ご家庭の都合や子どもの成長に合わせて選んでよいのです。
こちらの記事で、七五三を数え年と実年齢で行うメリット・デメリットを解説しているので、チェックしてみてください。
早生まれの場合は?
早生まれは、1月1日から4月1日までに生まれた方を指します。
早生まれの場合、実年齢(3歳、5歳、7歳)で七五三を行うと同学年のお友達と一緒のタイミングでお祝いができなくなってしまいます。
11月15日時点でまだ誕生日を迎えていないため、厳密には1つ下の学年と七五三を行うことになるのです。
そのため、早生まれの子どもは数え年の年齢を選ぶことで、同学年のお友だちと同じタイミングで七五三のお祝いができます。
コロナで変わった七五三の新しいカタチ

コロナ禍の七五三はどうだった?
コロナ禍では緊急事態宣言を受け、七五三も自粛傾向にありました。
神社やお寺では、参拝時間の短縮や本殿に入れる人数制限等があり七五三の分散化が広く呼びかけられました。
遠方に住んでいる両親や祖父母との七五三を自粛するご家庭も多くあったでしょう。
同居の家族だけで七五三のお祝いや、秋にこだわらない七五三、1年ずらしてお祝いをするなど各ご家庭によるお祝いの仕方が定着しました。
七五三は写真撮影がメインイベントに
七五三の写真撮影は、子どもの成長記録を残すものとして欠かせないイベントですが、今や参拝・会食よりも写真撮影がメインとなっています。
ご家庭ごとの七五三のお祝いの仕方が主流となり、七五三は写真撮影だけというのも一つの選択肢です。
子どもの成長を喜ぶ気持ちを写真で残すお祝いの仕方でもよいのです。
特別な衣装を着て、スタジオで写真撮影をする体験が、家族の大切な思い出作りになるでしょう。
前撮り撮影が定番化
七五三の前撮りとは、参拝日と別日に七五三の記念撮影をすることです。
大手フォトスタジオのデータによると半数以上のご家庭が前撮りを選択しています。
前撮り撮影時期も年々早まっている傾向にあります。
前撮りのメリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください!
まとめ
七五三はいつ?といった基礎知識から、2023年の七五三事情についてまとめました。
- 七五三は人生の通過儀礼のお祝い
- 一般的には11月15日だが、決まりはない
- 七五三の年齢は昔は数え年で行われていた
- 現在は実年齢で数えることが主流
- 数え年と実年齢を掛け合わせるなど柔軟に選択してOK
- コロナ禍で各ご家庭のお祝いの仕方が定着
- 今や七五三のメインイベントは写真撮影
- 前撮り撮影は定番化し、早撮りも人気
七五三は古くから受け継がれてきた伝統行事ですが、時代と共に七五三のあり方やお祝いの仕方は変化しています。
慣例にこだわるより、七五三の本来の意味である子どもの成長を家族で喜びあう気持ちを大切にしてお祝いしたいですね。